この記事では、ノーベル賞経済学者であり、また、思想家でもあるフリードリヒ・フォン・ハイエクについて、彼の代表的著作である『隷属への道(隷従への道)』を通してその思想を紹介したいと思います。また、記事内ではケインズとの対比なども紹介し、ハイエクの思想の特徴をわかりやすくまとめました。
- ハイエクはいつか読みたいんだけれども敷居が高い・・・
- ハイエクってどんな人なのか?ケインズとの対比を知りたい・・
- 『隷属への道』ってどんな本なのかを知りたい
- ハイエクとは保守主義者なのか、そうではないのか?
 しかの
しかの
こんな方に、まずはやさしくハイエクを知っていただき、いつか、『隷属への道』を手にとってもらえることがあればと思っています。
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
この要約を読む頃には、なぜ、彼が現在でも自由主義の大家として語り継がれている理由を理解していただけることでしょう。
コロナ禍により、世界中で多くの人が仕事を失い生活の手段を絶たれました。人々の生活を守るために金融・財政ともに政府が大きくなる時期ではありますが、一方で、ロックダウンやそれに伴う人々の自暴自棄により、我々の行為や思考から気づかないうちに自由が失われていく時期でもあります。これは、かつての1930年代の相似形とも言える現象で、今こそ、ひとりひとりが自由を真剣に考えることも大事なのではないでしょうか。
この時期だからこそ、ハイエクから学ぶことは多いのではないかと考えてこの記事を書いてみました。
目次
フリードリヒ・ハイエクとは?

フリードリヒ・ハイエクは1899年、オーストリアのウィーンで生まれました。
ウィーン学派といわれる経済学派の代表的学者の一人であり、1974年にはノーベル経済学賞を受賞しました。1944年に発表した『隷属への道』は、ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』、ミルトン・フリードマンの『資本主義と自由』と並び、古典的自由主義の三大古典と言われています。
『隷属への道』と時代背景
 ドイツのハイパーインフレーション
ドイツのハイパーインフレーション
初版が発行された1944年は第二次世界大戦中でした。当時、ドイツはナチスによる国家社会主義独裁政権による全体主義体制の下にありました。多くの人は、それはドイツに固有のものであると考えていましたが、ハイエクは当時、次のように主張しました。
その上で、「第二次世界大戦が終結した暁には、自由主義諸国がファシズム国家と同じ過ちを犯さないために、自由について考えなければならなくなる」という問題意識を持って、『隷属への道』を書いたのでした。後述しますが、第二次大戦後のイギリスなどは「ゆりかごから墓場まで」を標榜した福祉政策が取られましたが、それが最終的には70年代のイギリス病につながる問題へとなりました。
現代との共通点
ハイエクが『隷属への道』を書いていた時期というのは民主主義国家ドイツが集産主義化・国家社会主義化していく流れと重なった時期でもあります。かつて、最も民主主義的とも言われるワイマール憲法を冠したドイツが、自ら民主主義を停止して全体主義化したきっかけは、第一次大戦の戦後賠償と1929年から始まった世界大恐慌による経済崩壊です。
このダブルパンチで人々の生活は破壊され、多くの人は絶望します。
こうなると、分断された個人は大きな存在にすがりつくようになります。
この人々の心理的傾向をうまく掴んだのがナチスでした。
ナチスはシャハト博士の経済政策を採用し、いち早く大恐慌からの脱却に成功します。人々は興奮し、ナチスの政策が人道的に正しくなかろうが闇雲に賛同していくことになるのです。
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
 しかの
しかの
ハイエクとケインズ
 ハイエク(左)とケインズ(右)
ハイエク(左)とケインズ(右)
ハイエクとケインズは一般的に対比される関係にあります。
ケインズといえば、ニューディール政策の理論的背景であるというのは有名でしょう(厳密には、ニューディーラーがケインズを参照したわけではないです。)。ニューディール政策とは、1930年代前半に米国民主党よって行われた政策です。一方、米国共和党の保守派やティーパーティーなどが依拠するのがハイエクのような自由主義理論です。
すなわち、両者が政策にもたらした影響は、ある意味で正反対であると言えるでしょう。
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
 しかの
しかの
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
どちらが正しいという論争をするのではなく、それぞれの理論が登場した背景を理解して経済情勢に合わせて組み合わせていくことが良いのではないでしょうか。ケインズはまさに大恐慌の時代を目撃して、急速なデフレ化と貧困化から脱却するために一般理論を出版しました。一方で、ハイエクは同様に大恐慌を通じて人々が自ら自由を放棄して、全体主義化していく流れを観察していく中で『隷属への道』を出版しました。
私はどちらの考え方も正しく、そして、処方箋を間違わずに使い分けることが大事だと考えています。
ケインズ経済学については、その代表的書となる『雇用、利子および貨幣の一般理論』を通じて解説を別途行っていますのであわせてご参照ください。
下記の本は代表的な「ケインズとハイエク」の対比を書いた本です。
『隷属への道』のあらすじ
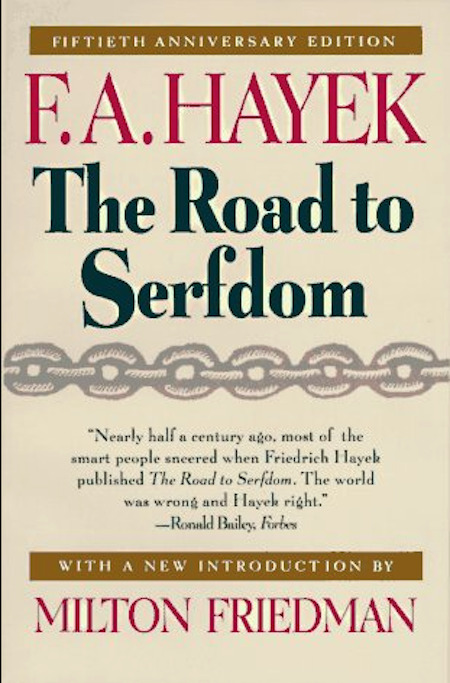 『隷属への道』のあらすじ
『隷属への道』のあらすじ
本書は自由主義の名著とされている、ある意味では理論の書ですが、一方で、具体的な事例への言及も多く、また小節に分けられていることもあり、非常に読みやすいです。読書になれてない方には、はじめは敷居が高く感じるかもしれませんが今のような時代だからこそ、『隷属への道』を読むことで今後の示唆を見出すことはとても価値があるのではないでしょうか。
『隷属への道』のあらすじ
ここでは章ごとに簡単なあらすじを紹介します。
第1章「見捨てられた道」
自由主義社会で自由主義が失われていった理由を解説したものですが、いきなり、現在の日本に重なる部分が多く、日本人への示唆に富む内容になっています。
第2~3章「社会主義の性質」
第2・3章では「自由」とは何なのか、社会主義者が使う「自由」ではなく、自由主義が使う本当の「自由」とは何なのかが解説されています。第2章は「大きなユートピア」、そして、第3章では「個人主義と集産主義」とタイトルがつけられています。
第4~6章「計画化について」
第4〜6章は計画化についてです。計画化が我々にとって不可避であるというのは間違いであること、また、計画化が民主主義や法の支配とは両立し得ないことが解説されています。
第7章「経済統制と全体主義」
第7章では計画主義者による、中央統制は、経済的問題にのみ適用されるだろうという方便に対する反論がなされています。経済の統制は全活動の統制と同じなのだということです。
第8章「だれがだれを支配するのか」
第8章では主に社会主義が抱える矛盾が解説されています。多くの人が支持する理想的なテーゼの裏には、あまりにも多くの現実的な欠点や矛盾を孕んでおり、彼らが掲げる理念は机上の空論にしか過ぎないことが解説されています。
第9章「保障と自由」
第9章は保障についてです。自由を守るために必要な限定的保障と、自由主義社会では成立し得ない絶対的保障の違いや、保障そのものやそれを拡充するための官僚国家が、自由主義にとっていかに恐ろしいものであるかが解説されています。
第10章「なぜ最悪なものが最高の地位を占めるか」
第10章は社会主義者によく見られる迷信、すなわち、過去の独裁者がならず者であったのは、全体主義の本質ではなく、むしろ歴史的偶然でしかないのだという嘘について反論しています。
その上で、集産主義は排他的でしかあり得ず、また、独裁権力が道徳的であることはあり得ないという事実が、全体主義の抱える構造的な運命であるということが解説されています。
第11章「真理の終焉」
第11章は前章をさらに踏み込んだ内容で、全体主義国家では、倫理的価値を統制するために、あらゆる道徳の基礎の一端を担っている真実さえも歪める必要があると言うことが解説されています
また、自由主義社会の中にある個人主義こそが、本当の意味での真実を守ることができ、異なる知識や意見を持っているものとの相互作用による人類の理性の成長を守ることができるという主張がなされています。
第12章「ナチズムの社会主義的根源」
第12章ではナチスドイツについて解説されています。その中で、全体主義と社会主義の関係性や、それらが個人よりも国家や社会といった組織に価値を見出していたことが詳しく述べられています。
第13章「われわれの中の全体主義者」
第13章は当時の英国にいた全体主義者思想家の話です。時代背景を扱った章で述べた通り、ハイエクはドイツが歩んだ独裁国家への道はドイツに固有のものではないと考えていました。
本章では、英国の中の有名な著述家や科学者の言葉を引用する形でそのことについて述べています。この章を読んでいると、今の日本に重なる部分が非常に多く、危機感を感じられずにはいられません。
第14章~16章「まとめ」
14章以降はおもにまとめです。ここまでにわたって話してきたことを振り返っています。また、時代背景を扱った章で述べた問題意識に関して、英国人(自由主義陣営)に求められる行動についても語っています。
第14章では、自由主義について国際的な視座から言及がなされています。驚くべきは欧州の未来への予測の正確性です。
現在のEUの現状にぴたりと当てはまっているのです。
『隷属への道』の購入について
『隷属への道』ですが現時点ではKindle版はありません。
したがって、購入はすべて文庫本・単行本での購入となります。とはいえ、これだけのボリュームのある本ですので、Kindleで読むよりは紙の本で読むほうが理解を助けてくれるので良いのではないでしょうか。現在、ネットで購入しようすると2版でております。私のレビューははじめの西山千明訳『隷属への道』(春秋社)をベースに行っています。最近では、村井章子訳の『隷従への道』(日経BPクラシックス)というものも出ております。
どちらが良いかは皆様のご判断にお任せします。
ハイエクによる自由主義思想のエッセンス
ここでは、『隷属への道』の中に出てくる重要なポイントについて紹介してします。ただし、これらを理解するためには本書を読んでいただく必要があることは言うまでもありません。まずは、本著の中での主張やその他著書の中からピックアップした部分を見ながら考えていくことにしましょう。
自由主義者の主張は、諸個人の活動を調和的に働かせる手段として、競争というものが持つ諸力を最大限に活用すべきだということであって、既存のものをただそのまま放っておけばいい、ということではない。
自由主義者は、政府は常に小さくあるべきだということを主張していますが、それは政府が必要ないということとは全く異なります。自由主義の理解には欠かせない重要なポイントです。
短期的に見れば、多様性と選択の自由のために払う代償は、時に高くつくかもしれないが、長期的に見れば、物質的な進歩でさえも、この多様性に支えられている。
計画化が必要であるとされる根拠の一つである、新しい技術の実用化には、競争からの保護が必要であるというものがあります。しかし、計画化が本当に行われれば、新しい技術さえも生まれないことになるのです。
経済的自由は、他者のどんな自由にも先立つ前提条件であるが、社会主義者が約束するような「経済的心配からの自由」とはまったく異なっている。後者(前述)の自由とは、個人を欠乏から遠ざけると同時に選択の権利からも遠ざけることによって初めて獲得しうるものである。
日本のみならず世界中で、長い間、「自由」という言葉は本来とは違う意味合いで使われてきました。いわゆるリベラルに分類される人たちが、手厚い社会保障を求めたりしているのです。
しかし、彼らの主張は、本来の意味の自由、それは自由主義者の使う自由とは明らかに違います。その一例がこの引用の示すところなのです。自由とは、本来は選択の権利のことを示しているのです。
全体主義(集産主義)については、かなり深く考察をしていますが、基本ハイエクの主張というのは「全体主義というのは民主主義の帰結である」という結論です。このあたりは、以前、別のエントリでも紹介したエーリッヒ・フロム、オルテガ・イ・ガセット、そして、トクヴィルなども似たような主張をしています。
つまり、19世紀以降の自由主義(主に積極的自由)に個人が耐えられなくなった帰結だということなんですよね。ハイエク自身も、
(自由主義の成功こそが、自由主義そのものの衰退の原因となった)
タブーに挑んだハイエク
さて、ここで南米の2つの政権の進んだ道を見てみることにしましょう。
1つはアルゼンチンのアジェンテ政権。史上初の民主主義手続きを通じて誕生した社会主義政権。多くの企業の国有化、そして、農地改革により土地が国有化され農民に分配された政権です。
もう1つはチリのピノチェト政権。悪名高き独裁政権ですが、経済については自由主義的体制を取り続けました。
行為の自由と自生的秩序 – 2つの自由からの考察
ハイエクの指摘で興味深いのは、人々の自由こそが最上のものと考えました。ハイエクは『自由の条件』の冒頭で「自由」概念の定義をこのようにつけています。
「自由」とは「社会において、一部の人が他の一部のひとによって強制されることができるだけ少ない人間の状態」とされている。そしてそこでいう「強制」とは以下のものを指すとしている。「強制」とはある人の環境または事情が他人によって支配されていて、より大きな害悪を避けるためにその人が自分自身の首尾一貫した計画に従うのではなく、他人の目的に奉仕するように行動を強いられることをいう。他人によって強いられている状況のもとでより少ない害悪を選ぶ以外は、かれは自身の知性または知識をもちいることもできなければ、自身の目的と信念に従うこともできない。
ここにハイエクの思想の中で自由というものが2つあることに気づきます。
1つは「経済的行為の自由」、そして、もう1つが「言論・思想などの(知的領域の)自由」です。
我々は自由というと後者の「言論・思想の自由」すなわち「知的領域の自由」を重視します。だからこそ、中国などのような独裁体制の国に厳しい視線を注ぐわけです。一方で、ハイエクはより厳密に職業選択、財産処分など経済行為に関する自由も非常に重要であると述べました。なぜなら、経済的自由、つまり、「行為をすることそれ自体の自由」がない社会では、人々のトライアンドエラーを通じた自生的秩序が誕生するチャンスを奪うと同時に、最終的には、全体主義・集産主義へ傾倒していくと看過したからです。
行為の自由の価値を犠牲にして知的自由の価値を称賛するのは、大建築物全体のうち最後の仕上げの部分をとりあげるようなものである。われわれが議論すべき新しい考えを持ち、調整すべき多様な意見をもつのは、これらがつねに新しい環境のものとにおける個人の努力から生ずるのであって、かれらはその具体的な仕事にさいして自分たちが学んできた行為に関する新しい道具や形式を利用するのである。(『全集I-5』)
タブーへの挑戦 – 民主主義と自由主義、どちらが大事なのか
ハイエクは、経済的行為の自由が少ない中で、思想の自由があったところで意味がないと考えたのです。それが、先程の南米の2つの政権の話にも繋がります。
彼は極端な話ですが、民主主義よりも人々の自由が大事であると考えました。
つまり、「民主主義下での経済的自由がない社会」と、「独裁・寡頭体制下の経済的自由がある社会」ではひょっとすると後者のほうがマシかもしれないという、ある種の禁断のオルターナティブを提示したわけです。言い換えれば、民主主義と全体主義が結びつく可能性を捨てきれなかったのでしょう。これは、ナチズムやスターリニズムのあった時代にはとても勇気のいる議題提示だったのではないでしょうか。
 しかの
しかの
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
 しかの
しかの
自由主義は、ヒトラーが最も憎んだ教義であるという名誉を持っている
このような「独裁」と「自由」の組み合わせが存在しうる可能性を提示したことはとても興味深い話です。おそらく、ドイツ、イギリス、そして、アメリカと自由主義国家にいたハイエクにとって、民主主義の中には時と場合により自由主義と対立する可能性を見出していたのでしょう。つまり、民主主義と全体主義が一体化するリスクです。
漠然と考えていた自由を深く考えるにはハイエクは最適な教材であると言えるのではないでしょうか。
ハイエクの保守性と保守主義との違い
ハイエクの理解にオススメの書籍
まとめ〜隷属への道をいま読む意義
2020年現在、日本は自由民主党が与党で、野党には立憲民主党、共産党、また少数政党がありますが、野党はグダグダで与党に対してしっかりとした対抗軸を打ち出すことができなくなっています。コロナ禍で民間企業や個人事業主の多くがダメージを被った結果、多くの人々が職を失い、また、大学を卒業して社会に出るはずの学生たちは仕事が見つからない状況にあります。
この状況こそが、世界大恐慌が起きた1920年代から1930年代の相似形とも言える状況なのです。
この状況下で、かつては、各国政府はいち早く大きな政府になることで大恐慌から脱出しようとしました。この事自体はやむを得ないとも言えますが、一方で、ハイエクが指摘するように、民主主義国家における様々なセクターの国営化や福祉国家化は長期的には社会主義化、全体主義化へとつながるリスクを内包しています。
いま『隷属への道』を読む意義とはなんでしょうか。
これこそが、コロナ禍の世界への問ですが、その回答は、1994年版へ向けられた本著の序文の中で、ミルトン・フリードマンが次のように答えています。少し長いですが、大事なところですので引用しておきます。
政府のいっそうの拡大においては、もはや力点は政府が直接に生産活動を管理する点に対してではなく、おそらく民間の諸企業に対して間接的な規制をすることであり、またさらには所得移転という政策に変化していった。この政策の現実の中味は、政府がまったく恣意的に国民の一部から税金を略奪して、国民の他の一部に譲渡金として与えるということでしかない。これらの政策のどれもが全て平等と貧困の根絶のためという名のもとになされてきている。しかし、これらの社会福祉政策は、そのどれもが原理原則を欠いてコロコロと変化しており、相互に矛盾した諸要素の混合でしかない補助金を、各種の特殊利益グループへ与えているにすぎない。
この文章を読んだとき、まさに今の日本のことを言っているということに驚きを感じずにはいられません。日本では許認可(規制)の数が現在も一日一個のペースで増えています。また、先日、医療保険の高齢者負担率について、与党である自民党と公明党が揉めていたというニュースを目にした方もいるでしょう 。
つまり、日本では経済的な自由が犯されており、その程度は日々拡大しているのです。このことを日本人が自覚しない限り、日本が再び経済成長することが出来ないだけではなく、いつか政治的な自由さえも奪われてしまいかねないのです。
さらに、当初は人々の良心によってはじまる全体主義化が最終的には独裁体制、人々の弾圧に帰結するメカニズムについてもこのように論じています。
個人主義的な諸目的の大半を支持して公言する人々の多くが、矛盾だと認めることなしに、集産主義的手段をそれらの諸目的達成のための手段として支持している。社会の諸悪は邪悪な人々の活動によって発生させられるのであって、(自分たちのような)善良な人々が権力を振るいさえすれば、すべてはうまくいくと信じることは、心をそそる考えではある。
しかし実際は、邪悪を生み出すのは権力の座にある「善い」人々である。反対に、善い結果を生み出すのは、権力は持っていないが、隣人と自発的な協同のための活動ができる「普通」の人々だ。これを理解できるようになるためには、感情抜きの分析と思想とが不可欠であり、もろもろの感情を理性的な機能力へと従属させなければならない。
世界の主に先進国と言われる民主主義国家で、1930年代とほぼ同じ展開をたどりはじめていますが、このフリードマンの指摘が当たらないことを祈るばかりですが、人々の多くが、自発的に自由を放棄し緊急事態宣言とロックダウンを求めている現状を見ていると、日本では先立った過度な福祉国家化が既に人々の自由を奪っていたと見ることもできるかもしれません。
 サイト管理人:大山俊輔
サイト管理人:大山俊輔
しかし、その最終目的地は全体主義化であることを今理解しておく必要があります。

最後に、本書の中で引用されている、ベンジャミン・フランクリンが述べた言葉を紹介しておきます。
ほんのしばらくの安全を手に入れるために、本質的で不可欠な自由を放棄してしまう人々は、自由も安全も持つ資格がない。
この言葉ほど、辛辣で厳しい言葉でありながらそれを実現できる社会ができることを願わない言葉はないのではないでしょうか。
しかの&大山俊輔

』からハイエクをわかりやすく解説-940x529.png)




